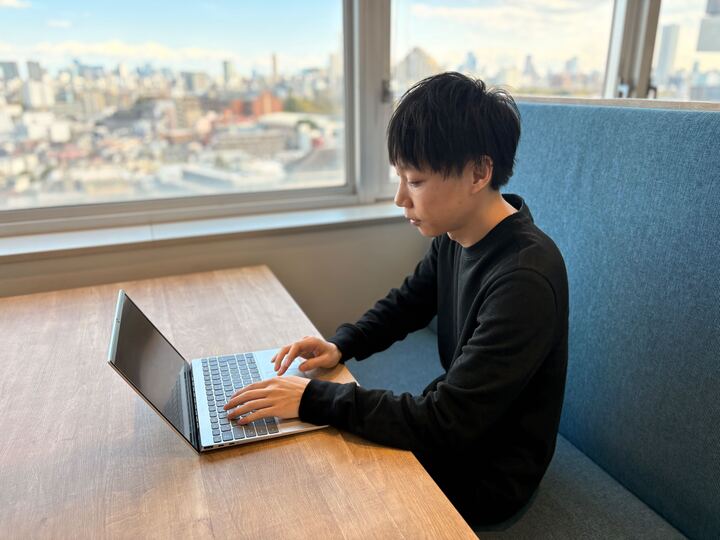2025年は早くも3分の1が過ぎ去り、桜は瞬く間に散り、蒸し暑さすら感じる季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
春は、別れがあれば出会いもある。WESEEKも例外ではなく、3月までに数名のインターン生が卒業し、新規インターン生が続々と応募・入社しております。創業20周年を迎える2025年度も、私たちと共に歩むインターン生との出会いを心待ちにしています!
インタビュー後半戦
こんにちは。戦略企画室インターン生の黒川です!
本ブログは『武井さんにインタビューしてみました(上)』の続きとなっております。まだ上巻をご覧になっていない方は、そちらもチェックしてみてください!
今回の内容と目的
インタビュー前半では、WESEEK代表・武井さんに、IT企業そのものやWESEEKについての予備知識(普段どんな仕事をしているか、どんな風に働いてるか、etc.)を持たない人間の目線で、疑問に思ったことを訊ねていきました。
今回はインタビュー後半のようすをお届けします!今回取り扱う内容は、大きく分けて2つです。
1つ目は、WESEEKの戦略企画室について深掘りしていきます。WESEEKならではの個性的な部署名ということもあり、企画室への配属を希望したインターン生は、採用面接にて武井さんから企画室の業務について説明を受けることになります。
2つ目は、WESEEKに入社するインターン生への思いを伺います。約10年前からWESEEKは多くのインターン生を受け入れており、おおよそ正社員と同数のインターン生が在籍しています!これは他の企業と比較して特徴的な側面であり、「社員・インターン比を4:1に統制する」といったことを行っていません。
2025年度もこれまでと同様、エンジニア・デザイナー・企画室のすべてにおいて、インターン生を積極的に募集中です。「自分の得意なことを仕事で発揮したい」「スキルを磨きたい」「現役のプログラマーと一緒に働いて刺激を受けたい」そんな学生の皆さんをお待ちしております。
戦略企画室の業務をご紹介
参考までに、企画室インターンで定型的に行われている業務を4つご紹介します。特にインタビュー前半はこれらの内容を前提に話が進みますので、ご一読ください↓↓↓(より詳しく知りたい方はこちらをクリック)
①社内イベントや福利厚生制度を発案・実行します
社内イベントについて詳しく知りたい方はこちらをクリック
②ブログを書きます
社内イベントなどのWESEEKでの出来事や、社員・インターン生へのインタビューなどを発信しています。定期的に更新しているので、気になったものから遡ってご覧ください!
③社内通貨"WSD"を管理します
社内のコミュニケーション活発化をねらった、WESEEK独自の通貨制度です。「通貨」としたことで、単なるポイント制度にはない長所が生まれました(後述)。主に、同僚への日頃の感謝や退職する方へのお別れの言葉などを送信したり、講習会を主催、あるいはそれに参加したりすることで、企画室から社員に通貨の流れが発生します。社員はその通貨を使用して、企画室が提供するサービスを購入することができます。
④SNSを運営します
広報活動に意欲的なインターン生が入ると更新が活発化します。私もいろいろ投稿案を練ってるので更新をお楽しみに~ 主にInstagramを運営してます。リンクはこちら
企画室では、各インターン生がオリジナルの施策を編み出し、会社をよりよい方向へ成長させるための業務を行っていきます。
以上を踏まえ、インタビュー後半の目的を以下のように設定します↓↓↓
「自身はエンジニアである武井さんが、会社を経営する立場になって、エンジニアとは別に『戦略企画室』を設定し、インターン生を多く受け入れるスタイルを採るようになった理由・背景を探る」
インタビュー再開

戦略企画室について
戦略企画室が生まれた流れ
―戦略企画室自体は、どういった経緯で誕生したのでしょうか?
ウチは創業当初から社員の大半がエンジニアで、彼らにはプロのエンジニアとして業務に集中して欲しかった。そうすると、エンジニアリング以外の雑務をどう処理するか問題になります。昔、社員6,7人とかで運営してた頃は事務経理のアルバイトの子が1人いたので、ひとまずその子にやってもらってました。だから一応、雑務を担当していた総務部が"戦略企画室"の原型ではあったね。
その後、会社規模が少し大きくなり、フルタイムのバックオフィス担当が必要となるフェーズになりました。ただそこで、WESEEKっていう会社にエンジニアとバックオフィス担当社員が共存したとき、仕事に対する熱意のギャップが生まれる予感がして。それは何としても避けたかった。バックオフィス担当の人に「あなたの仕事は主に雑務です」って僕から伝えといて、社員面談で「自分の人生について一生懸命考えてますか?」とか訊かれたら、間違いなく困惑されるよな、と。
僕は起業当初から、エンジニアと同等の熱意で会社作りに励む機関を置きたかったんだよね。その想いを核として設計したのが"戦略企画室"です。エンジニアたちの仕事のパフォーマンスを維持・向上させる施策を提言することで、彼らが仕事に集中できる環境を造り、結果としてWESEEKの業績を上げるのがねらい。原型の総務部からだいぶテコ入れが入ったね。
―かなり試行錯誤があったんですね。
そうだね。とはいえ自分が会社経営を通じて実現させたいこと自体は変わってない。企画室に要求してることも変わってない。けど、7年前くらいに戦略企画室という組織について本格的に構想を練ってから、ぴったりな人材を入れるまで、道のりは長かった。今思えば理想が先行してたなとは思う。
6~7年前、当時企画室のインターン生だった太田さんが社員になってから今日まで、企画室は太田さん主導で動いてるんだけど…太田さんがエンジニアの人たちから仕事を褒められるのを見て、「あ、僕の狙いに近づいてるな」と直感したね。長年「戦略企画室ってどんな仕事してるかよくわからない」という課題を抱えてて、今も完全には解消できてはないんだけど、そんな中で太田さんは積極的にエンジニアの人たちとコミュニケーションをとってくれてます。
元々エンジニア志望だったことがプラスに働いて皆さんとのコミュニケーションがうまくいってるのかな〜と自分では分析しています。
何でも屋さん
―採用面接を受ける前、WESEEKの企画の仕事は「自社が開発した製品をどんな方針で売り出すか」といった、事業展開の計画を専門的に扱うと想像していました。ですが実際の勤務を経験して、「エンジニアやデザイナーが専門性を駆使して業務にあたっている一方で、戦略企画室は会社の経営を支える業務を幅広くこなしている」という印象を抱きました。「戦略企画室=何でも屋」という捉え方もできそうですが、武井さんはどうお考えですか?
まぁ、間違いではないですね、「何でも屋」は。何でも屋っていうのは、あらゆる手段を採るということ。業務上のタブーとか考えず、「これは自分たちの仕事じゃない」というマインドを捨ててもらう。これは、黒川君が入社前に想定してたようなマーケティング業務でも同じことが言えるようで、「モノを売るという目的を達成するためには、広告や宣伝をはじめ、あらゆる手段を尽くす」のが鉄則らしい。これも何でも屋と言える気がするね。
僕は起業してからずっと、仕事内容の境界線は基本的にぼかした方がいいと思ってる。エンジニア・デザイナーと企画室の境界線はさすがに乗り越え難いけど、前者は社員同士で専門領域を超えた職務を経験してもらってるし、後者も取り組む仕事の種類が膨大です。
正直、エンジニアはその専門性ゆえに「これは自分の仕事じゃないのでやりません」がある程度通りやすい職業だとは思うんだけど、戦略企画室はそういう思考に流されて仕事をしてはいけないと思う。手段を選ばずに会社の環境を改善して、魅力を高めることが至上命題だから。
例えば、消耗品の在庫確認とかって、率先してやろうとする人が出てきづらいと思う。そのとき「在庫確認はエンジニアの仕事じゃないと思うんで、企画室の人がやっといてください」「じゃあやっときます~」で現状を受け入れるんじゃなくて、「もっとスマートな在庫確認の方法」について真剣に議論するのが企画室の仕事であるべき。
―企画室へ抱く理想の大きさが窺えます。身が引き締まる思いです。
まぁ、僕が企画室に要求してることは多いと思う。その甲斐あってか、企画室の人たちは仕事の好き嫌いを意識しないクセが自然とついてくるような気がする。
エンジニアもそう。自身の専門外の仕事に手を出して、いろんな仕事を並行してこなすのが当たり前な環境を、エンジニア同士で構築しています。
―エンジニアの方々は、多様な仕事に触れるのをむしろ楽しんでいる感じでしょうか?
本人たちがそれを喜んでやってるかは、実際にアンケートをとってみないとわからないんだけどね。でもWESEEKという会社は元来、職種による境界に関係なく仕事をすることに価値を見出してる。それを社員たちが喜んでやってくれるように、僕も日々努力してますよ。
―「この仕事はやりたくない」と実際に社員から相談されたら、どう対処しますか?
ある程度要望を聞いてあげます。その結果、本人がやりたい仕事を今以上に覚悟を持って極めてくれるなら、僕も嬉しいから。ただ実際は、本人が極めたいと思ってる仕事が今のWESEEKに必要かどうかを考慮しなくちゃいけない。必要な仕事ならそれに特化してくれて構わない。
本人の要望が叶う・叶わないは関係なく、悩みを抱えて仕事して欲しくはないから、ヒアリングは欠かしません。
"改革者たれ"
―では、私が戦略企画室に触れた当初、印象的だったことについて伺います。インターンの採用面接や入社直後の面談で、武井さんが 「戦略企画室は改革者たれ」 と仰っていたのを鮮明に覚えています。あれは、どういった真意が込められていたのでしょうか?
さっき「企画室は何でも屋です」って言っといてアレなんだけど、「本質的には何でも屋じゃない」ってこと。こう考えるようになった象徴的なエピソードがあります。
数年前、エンジニア採用を全社を挙げて取り組むという機会があった。その時「自分が是非入社してほしいと思った方をスカウトする」いわゆる"ラブレター"を送るという作業を全社員で持ち回りでやろうと決めたことがあって。
そしたら、あるエンジニアから「それって戦略企画室の仕事じゃないですか、エンジニアの仕事ではないと思います」と意見が挙がった。そのとき咄嗟に、エンジニア・武井雄紀の戦略企画室スイッチがONになったんです(笑)「企画室は"専門外の仕事"を引き受けてくれる機関じゃない!」というスイッチが、理屈とかじゃなくて感情的に働いた。
さっき在庫チェックの例を出したね。企画室が何でも屋なら「在庫チェックはエンジニアの専門外だから企画室がやっておこう」になっちゃうけど、そうじゃない。「エンジニアの社員すら積極的に取り組んでくれそうなスマートな在庫チェックの方法」を検討すべきなんだ。そういうアプローチで会社を良いものにしてくのが理想的だと思う。
企画室は何でも屋なのは確か。だけど雑務をただこなす何でも屋になるのが企画室の仕事じゃない。「ルールを決めて会社の方向性を定める」、ここまでが企画室のみに課せられるべき仕事だと考えてます。
―そんなことがあったんですね…今それを振り返ってみたうえで、戦略企画室の人間に求めたい素質があれば教えてください。
企画室は、放っておいたら"改革者"から"何でも屋"になっちゃうので…そこで黒川くんたちに必要とされる素質は、「こだわりを持つこと」だと考えます。
僕なりに整理してみると…エンジニア・デザイナーなど世間的な肩書きがある人は、自分の仕事に自然と線を引きたくなる。一方で企画室は仕事内容に専門性がないから、放っておくといろんな仕事に手を出しちゃう。
前者は線がはっきりしやすいのに対し、後者は線引きが曖昧になりやすい。そこで、線がはっきりしやすいモノにはその線が曖昧になるような方向に、逆に曖昧になりやすいモノには明確な線引きをするという方向に、それぞれ力を加えてあげたいわけです。
多分だけど、「これは〇〇さんがやってよ」「その仕事は××さんに投げといて」みたいな、膠着した社会が嫌いなんだと思う。いろんな部署に橋を架けて、仕事を通じてみんながつながっていく。WESEEKではそういう社会を形成していきたいね。
社内通貨"WSD"(WESEEK Dollar)